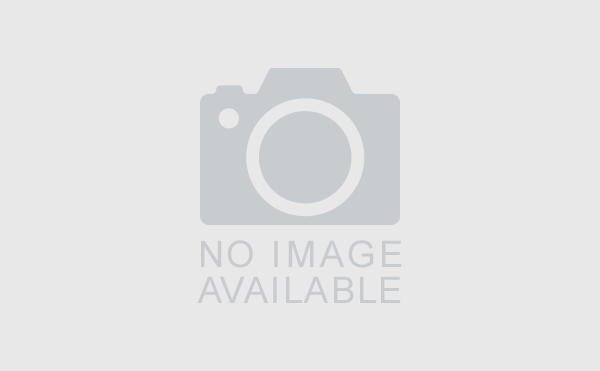🌺沖縄のサンゴ礁が危機に瀕しています|私たちダイバーができること
こんにちは。ダイビングインストラクターの吉野です。
私は沖縄の海が大好きで、年に6回以上は現地を訪れてダイビングを続けています。
しかし近年、その美しかった海に大きな異変が起きているのを、肌で感じています。
沖縄ではここ数年、かつてないほどの高水温に襲われており、多くのサンゴが白化現象を起こし、そのまま命を落としてしまっています。
🌊サンゴを追い詰める3つの大きな脅威
沖縄のサンゴが危機にさらされている理由は、ひとつではありません。複数の要因が複雑に絡み合い、サンゴの生態系が崩壊寸前なのです。
- 高水温による白化現象
地球温暖化により海水温が30℃を超える日が続き、サンゴと共生していた褐虫藻が逃げ出し、白くなって死んでしまう現象が多発しています。 - オニヒトデの食害
弱ったサンゴを狙うオニヒトデが大量発生し、サンゴを食い荒らしています。人為的な捕獲が追いつかず、壊滅的な被害を与えているエリアもあります。 - ダイバーによる物理的接触=人災
これが最も深刻な問題かもしれません。ダイバー自身がサンゴを傷つけているのです。
🤿なぜ人災が起こっているのか?ダイバーの質の変化
1980~1990年代、ダイバーは数も多く、意識も高く、講習内容も厳格でした。初心者と上級者を明確に分け、経験に応じたポイントで潜るのが当たり前でした。
ところが近年、ダイバー数の減少や経営的事情から、初心者と上級者が同じグループで潜るというケースが増えています。その結果、まだ経験本数が50本未満のダイバーが中性浮力もうまく取れないままサンゴ礁エリアに潜り、フィンやBCD、ゲージ、レギュレーターなどがサンゴに接触しても気づかないことが多くなっています。
これは、温暖化などの自然要因以上に深刻な問題です。完全に人災であり、私たちダイバー全体の問題でもあるのです。
🌍欧米のダイバーはなぜサンゴを守れるのか?
欧米では、オープンウォーターを取得した後すぐにアドバンスコースを受講し、さらに「ピークパフォーマンスボイヤンシー(中性浮力講習)」を当たり前のように受ける文化があります。
これは、「サンゴ礁のようなデリケートな環境に潜るには、それ相応のスキルと知識が必要」という意識が定着しているからです。
また、欧米のダイバーたちは
- フィンや器材が生物や岩に接触しないように泳ぐ
- 中性浮力を保ったまま水中で静かに移動する
- 自然への敬意を持ち、最小限の影響で潜る
といった行動を、習慣として実践しています。
そのため、オーストラリアのグレートバリアリーフやカリブ海のサンゴ礁は、観光地でありながら今も美しい状態が保たれているのです。
🏝️では、日本の沖縄県などのサンゴ礁はどうでしょうか?
残念ながら、環境保全への意識が低いまま潜っているダイバーが非常に多いのが現実です。
- 経験の浅いダイバーがサンゴ礁エリアに連れていかれる
- 中性浮力の練習が不十分なまま潜ってしまう
- 自分の器材がサンゴに触れても気づかない
こうした状況が日常的に起こっており、サンゴ礁の崩壊を加速させています。
これはもはや温暖化やオニヒトデ以上に深刻な「人災」です。
🧭インストラクターの責任|啓蒙とスキル向上の推進
インストラクターやガイドの役割は、単に水中を案内することではありません。私たちには、以下のような「教育者」としての責任もあります。
- アドバンスライセンスの重要性を伝える
- ピークパフォーマンスボイヤンシーの受講を推奨する
- 環境保全の観点から、スキル不足のままサンゴ礁エリアに潜らないよう伝える
- 「触れない・近づかない」意識を徹底させる
🐠サンゴ礁に潜る前に、私たちができること
沖縄のサンゴ礁を未来に残すために、今すぐにでもできることがあります。
✅ ダイバーとしての行動
- アドバンス講習を受けてスキルアップする
- 中性浮力を徹底的に練習する
- 器材の位置を把握して、接触を避ける
- 自然に敬意を持ち、静かな潜り方をする
✅ インストラクターとしての啓蒙
- 環境保護の知識をダイバーに伝える
- 初心者にはリスクの高いエリアを避けるよう指導する
- ブリーフィング時に環境配慮の注意喚起をする
📝まとめ|沖縄のサンゴ礁を守るのは、私たちダイバー自身
今、沖縄のサンゴ礁は本当に危機的状況にあります。
温暖化、オニヒトデ、そして人間による破壊が同時に進行しており、回復が追いついていません。
しかし、私たちダイバーの意識と行動が変われば、きっと未来にも美しい海を残すことができるはずです。
サンゴ礁の美しさに感動したことがあるすべてのダイバーに、いま一度問いかけたいと思います。
「あなたのフィンは、今日サンゴを蹴っていませんか?」
「あなたの浮力は、本当に中性でしたか?」
小さな意識の変化が、海の未来を守ります。