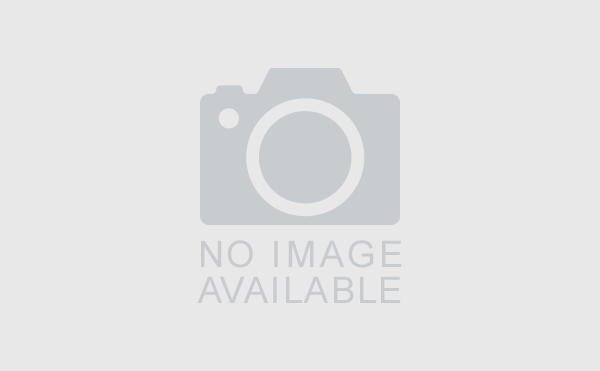体内窒素と減圧症の仕組み 〜安全ダイビングのための必須知識〜
体内窒素と減圧症の仕組み 〜安全ダイビングのための必須知識〜
私たちは日常的に1気圧(海面気圧)の中で生活しています。
体内の細胞や血液に溶け込んでいる空気(酸素・窒素・二酸化炭素など)も、この1気圧に平衡しています。
水圧の変化と体内窒素
ダイビングで水中に潜ると、周囲からの水圧は深度に比例して増加します。
- 水深0m … 1気圧(大気圧)
- 水深10m … 2気圧
- 水深20m … 3気圧
- 水深30m … 4気圧
この圧力変化により、空気中の窒素(N₂)は血液や組織により多く溶け込みます(ヘンリーの法則)。
例えば水深20m(3気圧)では、海面の約3倍の窒素が体内に溶け込んでいることになります。
潜水中は問題なくても、浮上時に圧力が下がると窒素は気泡化しやすくなります。
これが「減圧症(Decompression Sickness, DCS)」の発症メカニズムです。
減圧症を防ぐための浮上管理
浮上中は血液を通して肺から窒素を排出しますが、
血管径や循環能力、体質、疲労、脱水状態などによって排出速度は変わります。
このため、安全浮上速度が重要になります。
PADI基準では毎分18m(1秒に約30cm)を超えない速度が推奨されます。
しかし、水中で正確にこの速度を測るのは難しく、緊張時や流れのある環境では特に誤差が出ます。
ダイブコンピューターの役割
ここで欠かせないのがダイブコンピューターです。
コンピューターは以下の機能をリアルタイムで行います。
- 深度の継続計測
- 体内窒素の蓄積量をアルゴリズムで計算
- 無減圧限界時間(NDL)の表示
- 浮上速度の監視と警告
- 安全停止のガイド
このアルゴリズムは、世界中のさまざまな年齢・性別・体型の被験者データをもとに開発されており、安全性が非常に高く信頼できます。
「たった2メートル」の深度差が命取りになることも
水中では、見た目の距離感が陸上とは大きく異なります。
例えばインストラクターが岩の上(23m)で待機し、バディが岩の下(25m)で魚を観察していたとします。
見た目ではわずかな距離しか離れていないように感じますが、水圧は確実に異なります。
この2mの差で体内に溶け込む窒素量は増え、無減圧限界時間が短くなる場合があります。
もしインストラクターのコンピューターを共有して行動していると、
「インストラクターはまだ余裕がある」と思っていても、岩の下にいるダイバーはすでに限界を超えている可能性があるのです。
このわずかな差が、安全停止時間の不足や減圧症発症リスクの増大につながります。
だからこそ、ダイバー1人に1台のダイブコンピューターが必要なのです。
浅場こそ危険な理由
「浅いポイントしか潜らないからコンピューターは不要」と思う方もいますが、それも誤解です。
特に危険なのは、水深10mから水面までの区間です。
ここでは圧力が 2気圧 → 1気圧 に急変するため、窒素の飽和状態が大きく変わります。
最新コンピューターの進化
現在のダイブコンピューターは時計型が主流で、軽量かつ操作も簡単です。
Bluetooth接続でスマートフォンと連動し、潜水ログを自動で保存するモデルも増えています。
表示やアラームのカスタマイズができるモデルもあり、初心者からプロまで対応可能です。
まとめ
- 減圧症の予防には浮上速度管理が必須
- 体内窒素は水深と時間で変化し、わずかな深度差でも影響大
- ダイバー1人に1台のコンピューターが原則
- 浅場の浮上こそ慎重に
ブルーマリンでは、インストラクターとしての経験と長年の使用実績から、あなたのダイビングスタイルに最適なコンピューターをご提案できます。
安全で快適なダイビングのために、ぜひ一度ご相談ください。